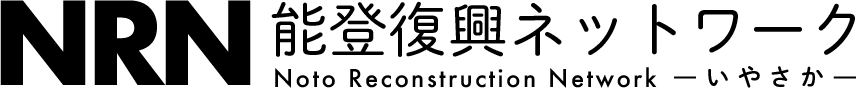「サステナブル」という言葉が、すっかり私たちの日常に溶け込みました。環境に優しい選択を意識する人も増えていますが、私たちは本当の意味で“自然と共に生きる”ことを、どれだけ実感できているでしょうか。
いま注目されている「リジェネラティブ」や「ネイチャーポジティブ」といった言葉は、未来への希望を感じさせる一方で、どこか遠い理想のようにも聞こえます。
でも、その実践のヒントが、実は日本の地域の暮らしの中にあるとしたら?
2024年の震災から再び歩みを進める能登半島。ここでは、世界農業遺産「能登の里山里海」に象徴されるように、人と自然が支え合いながら生きる営みが、今も確かに続いています。
農家の大森幸太郎さん、牡蠣漁師の山口夫妻──彼らの挑戦営みは、伝統の継承であると同時に、 私たちみんなでつくる“新しい地域の形私たちの未来”の始まりですもあります。彼らと共に、私たちも新しい地域の形能登の営みを次の世代へとつないでいく。私たちも、そんな第一歩を一緒に踏み出してみませんか?
「能登新鮮組」が耕す、里山里海の循環
能登半島は、三方を海に囲まれ、中央には緑豊かな山々が連なる、まさに「里山里海」を体現するような土地です。しかし、その美しい風土は、農業、特に野菜作りにとっては挑戦の連続でもあります。

七尾市中島町で、地域の若手農家10戸で結成された「能登新鮮組」を率いる大森幸太郎さん(42歳)。彼もまた、能登の風土に惹かれてこの地へやってきた一人です。地域の先輩農家から農業を学び、仲間と共に汗を流す中で、能登の農業に深く根を下ろしていきました。
能登の土地の多くは米作のための水田地帯。野菜を育てるための畑は、決して多くはありません。また、水はけが悪く、雨が降ると、ポンプで排水しなければ、畑に水が溜まったままになってしまいます。
そのような状況の中で、大森さんは農家として、経営者として、能登の伝統を未来へつなぐため、さまざまな試行錯誤をしています。

大森さんの農業は、大きく2つの柱で構成されています。
栽培のメインになっているのはジャガイモ、キャベツ、ブロッコリー、ネギ、ピーマンなどの加工用野菜の大規模栽培。中でもジャガイモは大手食品メーカーのポテトチップス用として契約栽培され、安定した収入基盤になっています。
もうひとつは能登ならではの伝統野菜の栽培。「中島菜」「能登娘(赤だいこん)」「小菊かぼちゃ」などの品種を少量多品目で栽培して、ポケットマルシェなどのECサイトで販売しています。
大森さん:「能登新鮮組では、大規模栽培だけでなく、少量でも価値の高い野菜を直接お客さんに届けることに力を入れています。ポケットマルシェのようなECサイトで、お客さんから直接『おいしかったよ』という声が届いたり、『こんな料理にしました』と写真をもらえたりするのが、何よりのやりがいです。ただ野菜を作るだけじゃなく、その価値をどう伝えて、適正な価格で買ってもらうか。それが一番の課題であり、挑戦ですね」
大森さんの農業は、畑の中だけで完結しているわけではありません。そこには、能登の里山里海ならではの、大きな自然の循環が息づいています。
例えば、地域の漁師から出る牡蠣の殻を、農家が肥料として譲り受ける慣習。これは大森さん一人が行う特別なことではなく、この地域に古くから根付く知恵です。海のミネラルが土に還り、野菜の味を深めるのです。海から得た恵みを、再び土へと返す。そんな持続可能な農法が、ここではごく自然に実践されています。

大森さん:「中島町の畑は海の真横にあるので、土に有害な成分が含まれていたら、そのまま海に流れ出てしまいます。ですから農薬は必要以上には使わず、化学肥料ではなく堆肥などの有機肥料を使うように心がけています。農業だけが良ければいいという考えでは、結果的に牡蠣の漁獲高が減り、その影響は巡り巡って自分たちにも返ってくる。だからこそ、地域全体のバランスを考えることが欠かせないのです」
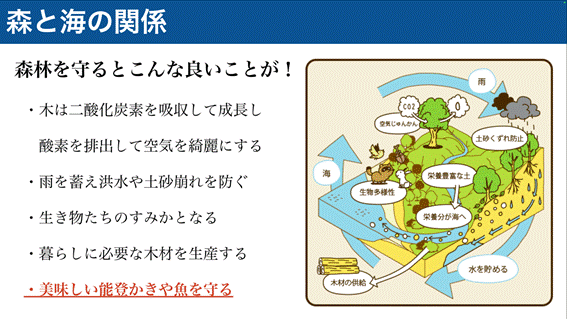
森を守り、海の恵みを未来へ繋ぐ「山口水産」の営み
七尾湾の穏やかな海で、代々牡蠣養殖を営む「山口水産」。家業に入った山口翔太 さん(30歳)は、小学生の頃からごく自然に家業を手伝い、いずれは漁師になるのだろうと感じていたと言います。
一方、妻の敦子さん(29歳)は兵庫県の出身。大学時代に能登で長期実践型インターンシップ「能登留学」を経験したことがきっかけで、能登の里山里海の魅力に惹かれて移住し、林業の仕事に就きました。
そんな二人が出会い、今では夫婦二人三脚で、山口水産の暖簾を守っています。

能登かきが多くの人を惹きつける理由は、そのおいしさはもちろん、特筆すべきはその安全性にあります。山々に囲まれた七尾湾は、川上から川下までの距離が短く、流域に住んでいる人は多くありません。そのため、生活排水が流れ込みにくく、豊かな山の栄養分が直接海に注ぎ込む豊かな漁場になっているのです。
そのおかげで、「過去30年以上、食中毒の原因となるノロウイルスの陽性反応が出たことは一度もない」と翔太さんは胸を張ります。

元々、「山の豊かさが、海の豊かさを育む」という考えから林業を仕事として選んだという敦子さん。海で牡蠣を育てるだけでなく、その源である山々にも目を向け、翔太さんと今でも森の手入れにも関わっています。
敦子さん:「元々林業に興味を持ったのは、私が好きな能登を守り続けるには、山を守ることが大事だという考えからでした。牡蠣が食べる植物プランクトンは、山の栄養塩で育ちます。つまり、山の状態が良くなければ、牡蠣が育つ豊かな海は守れません。だからこそ、私たちが山を守らなくていけないと思っています」
山口水産の「能登かき直売所」には牡蠣剥きをする加工場が併設されています。カチン、カチンと小気味よく響く殻を剥く音と、磯の香りが漂う加工場では、20年以上牡蠣剥きをしてきた熟練技術を有したスタッフが手際良く殻を剥いていきます。

殻を捨てた先は、外につながっており、そこは牡蠣殻の集積場。ここから牡蠣殻が運搬され、大森さんをはじめとする中島町の農家の畑へと撒かれるのです。

曾祖父の代から続くというこの加工場の仕組みを翔太さんは「アナログなようで合理的。改善できるか考えたことはあるけれど、結局思いつきませんでした」と語ります。
YouTubeでの情報発信や水福連携事業*、副業人材の活用など、先進的な取り組みにも積極的な翔太さん。その一方で、伝統的な能登の里山里海の循環は翔太さんにも脈々と受け継がれているのです。
*水福連携事業…水産業と福祉が連携し、障がい者等の水産分野で活躍を推進する取り組み
翔太さん:「能登の牡蠣を生産できているのも、里山里海の恵みがあるからです。牡蠣を守る前提として、里山里海を守っていかないと、能登の牡蠣も継続できない。今後はもちろん、牡蠣漁を継続させることも大事ですけれど、もっと里山里海に関心を持ってもらえるような取り組みを牡蠣漁師としてやっていきたいと思っています」
お祭りで継承される、世代と業種を超えた「里山里海」への想い
2025年9月20日、七尾四大祭りに数えられるお熊甲祭りが中島町で行われました。中島町の各集落にある19の末社から神輿が担ぎ出され、高さ20メールに及ぶ枠旗を掲げながら本社を目指して町を練り歩く、勇壮なお祭りです。

大森さんも翔太さんもその日は仕事を休み、それぞれの集落から祭りに参加しています。祭りは能登の風物詩。一年の中でも特に7月-9月は祭り囃子が聞こえない日はないというほど、いつもどこかで祭りが行われています。能登のお祭りは一次産業に従事する人々にとって、収穫や種蒔きの時期を知らせてくれる暦であり、日々の営みの一部でもあるのです。

なぜ、金沢から移住してきた大森さんが、先進的な考えを持つ翔太さんが、能登の里山里海への想いを受け継いでいるのか?なぜ、業種の異なる農業と漁業が互いを慮ることができるのか?その答えを解くヒントが「祭り」にあります。
祭りは、単なるイベントではなく、地域の人々が世代や業種を超えて顔を合わせ、互いの存在を確認し合うコミュニティの基盤なのです。
大森さん:「祭りで集れば、周りのことがよく分かる。だから、マナーを守ろうと思えるんです。特に里山里海について話し合ったりはしないですが、『こういうものだ』という暗黙のルールが、祭りを継承するとともに受け継がれているんだと思います」

自分の土地の草を刈り、周りに迷惑をかけない。農業で使う農薬が、海に影響を与えないように配慮する。一つひとつの行動が、能登の営みのバランスを考えた上で行われる。この、言語化されていないけれど誰もが共有している感覚こそが、能登の里山里海を、そして人々の豊かな暮らしを支えてきたのかもしれません。
そしてその感覚は、お祭りの文化を含む、能登の暮らしの中で育まれているのです。
あなたとの「つながり」が、能登と日本の未来を創る
能登の生産者たちが日々実践する、自然と共生する営みは、これからの社会における一次産業や暮らしのヒントを示唆しています。
一方で、この持続可能な循環を未来へ継承していく上で、その担い手たちは、今、いくつもの深刻な課題に直面しているのが現実です。

耕作放棄地を再生し、能登の農業を未来へ繋ぎたいという想いを抱く、大森さん。しかしその前には、震災以降に深刻化した人手不足という壁があります。野菜の植え付けや収穫といった最も人手が必要な時期に働き手が足りず、事業の拡大を阻んでいるのです。
販路や設備投資の課題も、大森さんの前に立ちはだかります。「中島菜」のような伝統野菜は販路が限られ、独自の価値を伝えるためには腰を据えたブランド育成をしなければなりません。また、新たな品種の栽培を始めるには、高価な専用機械の導入が必要です。

一方、山口水産もまた、人手不足の課題を抱えています。牡蠣の殻を一つひとつ手で剥く「むき身」の加工は、この道何十年というベテランたちの熟練の技に支えられてきました。しかし、震災を機に、その数は半分にまで減ってしまいました。
海にはたくさんの牡蠣が元気に育っているのに、その恵みを食卓に届けることができない。それが、今の山口水産が直面している現実です。だからこそ、山口夫妻は今、新たな仲間を模索しながら、事業の軸足を専門技術がなくても関われる「殻付き牡蠣」へと移そうとしています。スキマバイトや副業人材の活用など、これまでとは違う新しい形での関わりを求めています
能登の山海の恵みを店で扱いたい、マーケティングやブランディングが得意、能登の事業者とともに新たな事業をつくりたい、能登の生産の現場で働いてみたい──。今、能登にはさまざまな“関わりしろ”があります。そして、それはきっと能登の人々だけでなく、未来を生きるあなたの可能性も広げてくれるはず。
この記事を読み終えたあなたが、もし少しでも心を動かされたのなら、ぜひ一度、能登を訪れてみてください。能登は、あなたという新しい風を、心から待っています。